| 流動化処理土の『強度』は一軸圧縮強さで評価する。
一軸圧縮強さは、固化材や泥土の密度を調整することにより、用途に応じて100〜20,000kN/m2程度まで設定することができる。
流動化処理土の強度の特徴を以下に示す配合設計基準図を使い説明する。 図から同じ固化材量であれば一軸圧縮強さと泥土密度は比例する。一方、同じ強度に対して固化材量と泥土密度は反比例する。 例えば、一軸圧縮強さ300kN/m2に対して、泥土密度1.5t/m3のときC=100kgの組合せになるが、1.55t/m3とき80kg、1.60t/m3のときC=60kgのように、密度の増加につれて徐々に固化材が少なくなる。 この結果から、強度と水セメント比には一元的な関係がないことが推察される。また、泥土密度の変動が大きくなると同量の固化材では、目標とする一軸圧縮強さと差が生まれることが推察できる。 |
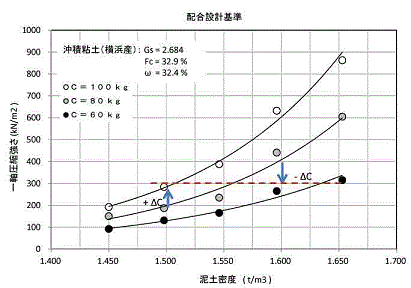 |
| 『強度』のもう一つの特徴は、泥土に含まれる砂分(粗粒分)の役割にある。 砂の強度への係わりについて実験をした。 まず、土に含まれる細粒分を分級して、水を加えて細粒分泥土を製造する。 次に、細粒分泥土に固化材を加えて流動化処理土を製造して一軸圧縮強さを求める。 続いて、同じ細粒分泥土(密度一定)に同量の固化材を加えたものに、砂を徐々に加えて密度が異なる流動化処理土を製造し、一軸圧縮強さを求める。 実験で製造した泥土密度に対して一軸圧縮強さをプロットしたものを図2に示す。 図中には、上で述べた方法で実験した4種類の配合(E〜H)の試験結果がプロットされている(細粒分の密度と固化材量が異なる)。 図の配合Eに着目すると一軸圧縮強さは、砂を加えて泥土密度が増えたにもかかわらず、同じ強度を示す。 他の配合F〜Hからも同様な傾向が読み取れる。 つまり流動化処理土中の砂分の増減は、一軸圧縮強さへの影響が少ない傾向が推察される。 この傾向が流動化処理土の『強度』のもうひとつの特徴になる。 このため原料土の粘土分と砂の割合が安定していると一軸圧縮強さは安定するが、粒度がバラツクと細粒分の絶対量が変わるので、一軸圧縮強さはバラツキはじめる。 |
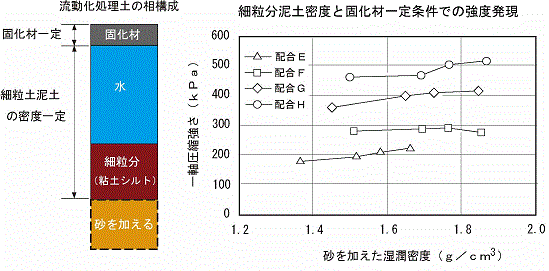 |
| 次に、流動化処理土は『強度』と『密度』を一体の品質として考えることにも特徴がある。 流動化処理土の『強度(一軸圧縮強さ)』は荷重で変形が進み土粒子と土粒子を接合するセメンテーション(固結)が破壊されるときの強さに関係する。 一方、『密度』はセメンテーションが破壊されたあとに現われる砂の土粒子間の接触摩擦による抵抗力に関係する。 密度が相当程度高ければ流動化処理土は、セメンテーションの破壊後に、引き続き荷重に抵抗するので大きな変形を抑制する働きがある。 『密度』の効果は、支持力や地盤反力係数とも関連し、密度が高いほど性能が高い。 通常、流動化処理土に荷重が加わると初めにパンチング破壊の現象が現われる(写真1)。 砂分が多く『密度』が1.6t/m3より高くなると、徐々に砂による接触摩擦の効果が表れる実験結果が得られている。 また、『密度』は流動化処理土の体積に占める割合(間隙)に関連し、『密度』が高いほど土粒子の割合が多くなり間隙が小さくなる。 すると流動化処理土の透水性が小さくなり(写真2)耐久性が向上し、水による浸食を抑制する効果が大きくなる。 |
.jpg) |